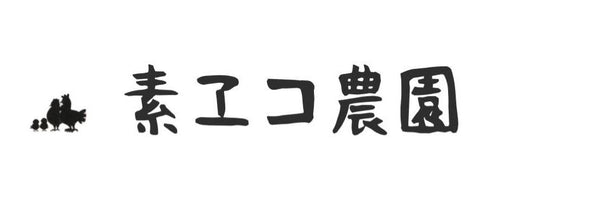「平飼い卵は美味しいけど高い…」──その疑問、実は日本の畜産がたどった歴史を知ると腑に落ちます。
本記事では、戦後〜現在までの卵価推移を振り返りながら、ケージ飼い普及と輸入トウモロコシ依存という 2つの転換点を解説。平飼い卵の価格が上がる理由をデータで示します。
1. 卵はいつから安くなった?
1951年の卵価は10個161円。当時の大卒初任給5,500円で換算すると現在価値で3,000円超/パックでした :contentReference[oaicite:0]{index=0}。高度経済成長が始まる1960年代に急落し、以後60年以上 200円前後で横ばい──これが「価格の優等生」と呼ばれる所以です :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

2. バタリーケージ導入と高度経済成長
1960年代、欧米型の多段ケージ(バタリーケージ)が日本へ一気に普及。 鶏舎1 ㎡あたりの飼育羽数が平飼い比5倍以上となり、人件費も大幅削減されました :contentReference[oaicite:2]{index=2}。 背景には伊勢湾台風(1959)後の復興支援で米国が推奨した集約畜産技術があり :contentReference[oaicite:3]{index=3}、ケージ飼いは「大量に・安く・均質に」卵を供給できる仕組みとして定着します。

3. 米国産飼料への依存構造
日本の飼料穀物自給率はわずか13%。トウモロコシの輸入量は世界第2位で、その ほぼ全量が畜産用です :contentReference[oaicite:4]{index=4}。 飼料価格の国際競争力と円高期の輸入拡大が、卵価を押し下げるもう一つの要因でした。
4. 平飼い卵が高い3つの理由
- 飼育密度:1羽当たり3〜5倍のスペース確保=鶏舎コスト増
- 地域飼料:輸入穀物を減らし地元米ぬかや規格外野菜を活用→原料費は上がる
- 洗卵・選別:地面産卵による汚れ除去と人工点検で人件費増
それでも私たち素ヱコ農園は、平飼い+地元飼料を選択。 鶏の福祉とフードマイレージ削減を優先し、直販で中間マージンをカットして価格を抑えています。

5. まとめ
卵が安いのは「技術革新と輸入飼料」に支えられた戦後モデル。 平飼い卵の価格には空間・手間・地域循環という付加価値が含まれます。 価格差の背景を知り、ライフスタイルに合った卵を選びましょう。
参考・出典
- 農林水産省「畜産統計年報(鶏卵価格推移)」2024年版 :contentReference[oaicite:5]{index=5}
- 東洋経済『卵はなぜ“価格の優等生”なのか』2023年 :contentReference[oaicite:6]{index=6}
- 日本養鶏協会『採卵鶏の飼養形態とコスト比較』2022年 :contentReference[oaicite:7]{index=7}
- 並松信久「高度経済成長期における食文化の変貌」2014年 :contentReference[oaicite:8]{index=8}
- 農畜産業振興機構「飼料自給率の現状と課題」2023年 :contentReference[oaicite:9]{index=9}
- European Commission “End the Cage Age” プレスリリース 2021年 :contentReference[oaicite:10]{index=10}
- House of Commons Library “Use of cages for farmed animals” 2022年 :contentReference[oaicite:11]{index=11}