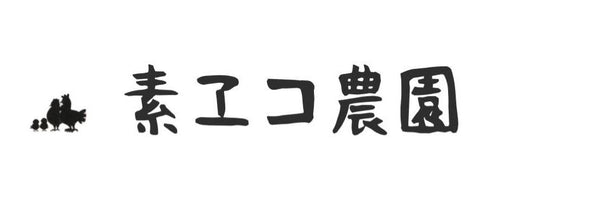最近、スーパーで見る卵の価格が高いですよね。
ちょっと前まで、1パック100円で、スーパーの特売品として扱われていました。
そんな卵も、最近では、10個入りで300円以上は当たり前になってきて、メニューからは卵が消えるお店も出てきました。
なぜこんなに値上がりしているのか?養鶏家ならではの視点で、お話できたらいいなと思っています。
卵の価格の上昇ー鳥インフルエンザ
卵の価格が上がっている要因はいくつかあり、鳥インフルエンザの流行、大手の廃業、飼料代の高騰、物価の上昇などがあります。

特に、今シーズンの鳥インフルエンザは過去最高の被害でした。
2023年4月上旬時点で、83件発生、約1500万羽殺処分されています。
これは、市場の鶏の1割以上の数字です。
鶏は卵を産むまでに半年間かかるので、回復するまでには結構な時間がかかると思います。
市場の1割の卵が急になくなったので、卵が足りない状態になり、卵の価格が上がったということになっています。
また、飼料代も昨年の秋頃から10年前の2倍近く上がっていて、養鶏家にとってはなかなか苦しい状況です。
飼料代は、国際情勢、通貨のレートなどに大きく左右されます。
飼料を海外に依存している体制などで、ここをどうにか国産に変えていくことも今後の食糧の安定供給を考える上では重要なテーマになってくると思います。
そもそも、なぜ安かったのか?

卵はこれまで価格が低く安定していて物価の優等生とも言われていました。
卵の価格は、高度経済成長以降、ほとんど変わっていません。
卵の価格が安定していた理由は、高度経済成長以降、日本の養鶏ではバタリーゲージが普及して、一つの養鶏で大量の鶏を飼育できるようなシステムが出来上がったからです。
それまで、日本の養鶏は、大量に飼育するのではなく、農家が副業的に数羽飼育していて、餌も食べ残りや野菜のくずで賄っていて、鳥の糞は畑にまいて、作物を育てるという小さな飼育方法でした。
そのため、昔は卵は滅多にあるものではなく、うちのばあちゃんは「卵は高級品で、風邪ひいた時しか食べれなかった」と言ってました。
1959年の伊勢湾台風以降、アメリカから集約的な畜産が輸入され、海外から安い飼料を大量に仕入れれることを前提とした工業的畜産が普及し、卵の価格が安くなりました。

日本人の食を支えている卵、1日に2個食べれるようになったのも、この工業的な畜産が発展したおかげです。
また、卵は毎日出るものなので、スーパーではフロント商品(赤字でもいいので、買ってもらって、他の商品を売るための導線)として使われていたので、価格が安かったとも言われています。
現在の日本の鶏の数
現在、どれくらいの鶏が日本で飼育されているのか想像できますか?
農林水産省のホームページで確認すると、令和4年2月時点で、飼養戸数は1,810戸で、前年に比べ70戸(3.7%)減少したそうです。
成鶏めす(6か月齢以上)の飼養羽数は1億3,729万1,000羽で、前年に比べ340万6,000羽(2.4%)減少してます。
そして、1戸当たり成鶏めす飼養羽数は7万5,900羽です。
この数字を見て、どう思いますか?
鶏は1羽につき1日1個弱の卵を産みます。
つまり、1億羽以上いるので、1日に1億個ぐらい生産されています。

鳥インフルエンザで、この安定が崩されしまったため、価格の上昇につながってしまいました。
まとめ
現在の卵の価格の上昇は消費者に負担をかけていると思います。いろんなものの価格が上がって、買い控えをする人も出てきています。
ただ、卵は完全栄養食で、また、調理をしやすいため、栄養的にも調理的にも必需品です。
養鶏場を実際に営むものとして、あえて言いたいのは、これまで卵の価格が安すぎたと思います。
現に、養鶏場は経営ができなくなり、どんどん廃業しています。
食を作る人が負担がかかり、食べていけない世の中になるもの辛いなと思います。
私は、素ヱコ農園平飼い養鶏を営んでいます。

現在、10個入り600~700円ぐらいで販売しています。燃料代や仕入れ価格が上がっているため、多少の値上がりはしましたが、一般的な卵よりも価格の上昇を抑えれています。
それは飼料を地元から調達したり、直売することで、為替や国際情勢とは関係が薄い養鶏場運営を行なっているからです。
もともと、通常の卵の3倍ぐらいでしたが、最近の情勢から普通の卵と比べても価格の差がどんどん縮まっています。
私たちの卵は、普通の卵と比べても2倍ぐらいしか差がないようになっています。
ありがたいことに、
「2倍しか差がないから、こっちの卵の方がいいね」って言ってくれる人が結構いらっしゃいます。
卵を作るのがだんだん難しくなってきていますが、頑張って良い卵を作っていきます