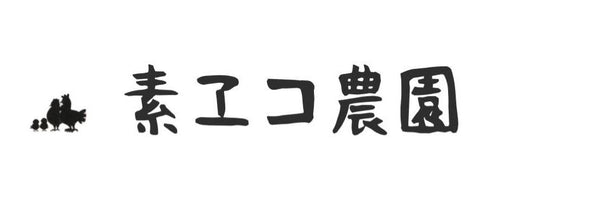【保存版】卵の賞味期限ガイド|見分け方・保存・サルモネラ対策を養鶏家が完全解説
卵かけご飯、オムレツ、ケーキ――卵は日本の食卓に欠かせない食材。
でも買いだめすると「これ賞味期限大丈夫?」と不安になることも。
本記事では平飼い養鶏の専門家・素ヱコ農園が、 卵の賞味期限の意味、サルモネラ菌との関係、正しい保存方法から 期限切れ卵の活用法までデータで解説します。
1. 賞味期限と消費期限の違い

- 消費期限=安全に食べられる期限(弁当・生菓子など)
- 賞味期限=おいしさが保たれる期限(比較的傷みにくい食品)
卵の賞味期限は生で食べられる最終ライン。 日本のガイドラインでは採卵日+14〜28日で設定するのが一般的1。 期限後でも十分に加熱すれば食べられます。
2. 期限を決めるサルモネラ菌と温度管理

卵白に含まれるリゾチームがサルモネラ菌の増殖を抑えますが、 活性は時間とともに低下。
10 ℃以下で保存すれば理論上57日生食可とする研究もあります2。 しかし家庭では温度変動が避けられず、安全側に倒して14〜28日に設定されます。

3. ヒビ卵は要注意
殻にヒビが入るとバリアが失われ、雑菌が一気に侵入。
生食はNGで、加熱しても1〜2日以内に食べ切るのが安全です3。
4. 賞味期限不明時の判定法
ボウルに水を張り比重テストを行います。
- 底に横たわる → 新鮮(生食◎)
- やや立つ → 鮮度低下(加熱推奨)
- 完全に浮く → 劣化(破棄)

5. 安全に長持ちさせる保存術
常温 vs 冷蔵
夏場やすでに冷蔵された卵は必ず冷蔵。 一度冷やした卵を常温に戻すと結露で菌が増えます。
尖った方は上でも下でもOK
最新研究では向きによる鮮度差は認められません4。
ゆで卵は日持ち短縮
リゾチームが失活するため、殻付き2〜3日/むき半日〜1日が目安。
冷凍テク
卵黄重量の20 %砂糖を混ぜてから冷凍すると、解凍後も滑らか。 業務用ベーカリーで普及するプロ技です。
6. よくある質問
Q1. 賞味期限切れでもにおいが平気なら生で食べられる?
A. 生食は避け、中心温度70 ℃以上1分以上の加熱を。
Q2. 茹で卵を冷凍したら?
A. 白身がスポンジ状に劣化するため推奨しません。
Q3. 冷蔵庫のドアポケットに置いてOK?
A. 開閉で温度変動が大きいので庫内奥に置くのがベスト。
Q4. 殻の色で賞味期限は変わる?
A. 殻色は品種差で鮮度とは無関係です。
7. まとめ
卵の賞味期限=生食安全ライン。 期限後も保存状態が良ければ加熱でおいしく食べ切れます。
素ヱコ農園の平飼い卵は採れたて発送で賞味期限約3週間。 定期便で常に新鮮な卵をどうぞ。
合わせて読みたい
LINEで卵の“困った”をその場で質問!
「黄身が崩れたけど食べて大丈夫?」「ヒビ卵はいつまで加熱でOK?」 素ヱコ農園の養鶏家が LINE公式アカウントでリアルタイム回答!
お客さま
黄身が崩れた卵って食べられますか?
素ヱコ農園
写真を見る限り腐敗ではなく黄身膜が薄くなる
「黄身落ち」の可能性が高いです。
においが正常なら加熱してお召し上がりください。
参考文献・出典
- 農林水産省『鶏卵の衛生管理指針』2023年.
- Humphrey, T. J. et al., “Influence of temperature on Salmonella growth in eggs”, International Journal of Food Microbiology, 2022.
- FAO/WHO, “Risk assessment of Salmonella in eggs”, 2021.
- D. Anderson et al., “Effect of egg orientation during storage”, Poultry Science, 2020.